本番が近づいているのに、ペーパーの正答率がなかなか上がらない…
そんなとき、つい焦ってしまいますよね。
「どのペーパーを優先したらいいの?」と迷ってしまうママも多いと思いますが、
そんなときこそ取り入れたいのが「お話の記憶」です。
「お話の記憶」に取り組むことで、記憶力・集中力・理解力が育ち、他
のペーパーにも良い影響が出てきます。
この記事では、我が家が実際にやって効果を感じた「お話の記憶」の練習法や、
苦手な子へのフォローの仕方を、体験談を交えてご紹介します。
焦りやすい直前期だからこそ、ポイントを絞って効率よく力をつけていきましょう。
どうして「お話の記憶」が大事なのか

小学校受験では、「先生の指示をしっかり聞いて、正確に行動できるか」がとても重要なポイントになります。
「お話の記憶」に取り組むことで、記憶力・集中力・理解力が自然と鍛えられていきます。
これらの力がついてくると、「お話の記憶」だけでなく、他のペーパーにも良い影響が期待できますよ。
「お話の記憶」ペーパーは必ず毎日取り組みたい

娘のペーパーの点数が伸び悩んでいたとき、塾の先生からもらったアドバイスは、
「お話の記憶ペーパーは毎日やりましょう」というものでした。
そこで、毎日の学習に「お話の記憶」を必ず取り入れるようにしたところ、
娘の正答率がぐんとアップ!
これまで何となくいろいろなペーパーを進めていたのをやめ、
「お話の記憶」に絞って取り組んだのがよかったようです。
コツコツ積み重ねることで、しっかり成果が出ることを実感しました。
「お話の記憶」に苦手意識がある場合の対処法
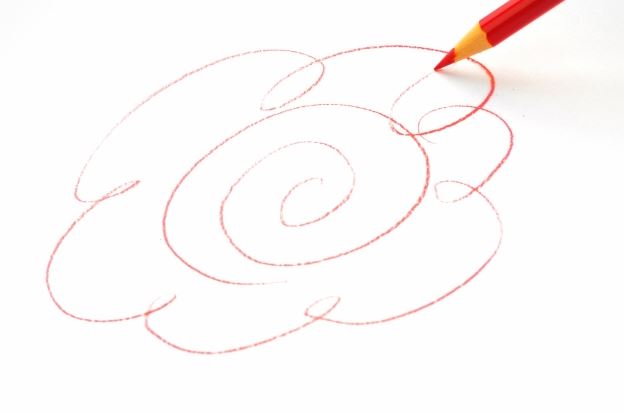
「お話の記憶」のペーパーは、お話が長く内容も複雑なことが多いですよね。
大人が一緒に聞いていても「難しいな…」と感じることもあるくらいですから、
苦手意識を持つ子が多いのも当然です。
我が子も例外ではなく、「次はお話の記憶やるよー!」と声をかけると、
あからさまにイヤそうな顔をしていました。
そんな娘が前向きに取り組めるようになったきっかけは、
同じペーパーを何度も解くことでした。
1回目は「ちんぷんかんぷん」でも、
2回目に取り組むときはすでに知っているお話なので、
「どこに注目すればいいのか」「何を覚えておけばいいのか」がわかるようになります。
我が家では、1回目と2回目はできるだけ間を空けずに取り組み、3回目は数日後にもう一度チャレンジする、という流れで進めていました。
回数を重ねるごとに娘も自信がついて、
花マルをもらうと、次の問題にも意欲的に取り組んでくれるようになりました。
まとめ
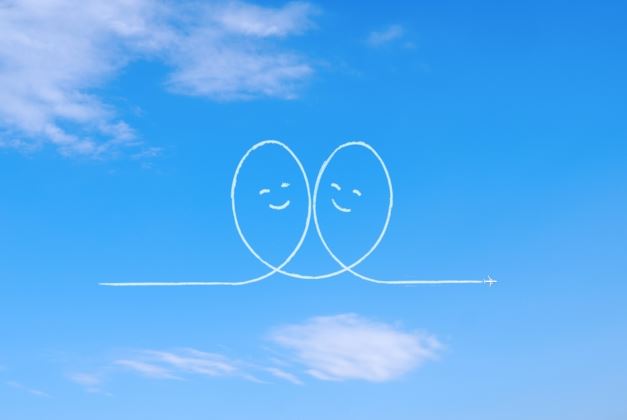
「お話の記憶」は、毎日の積み重ねが結果につながる単元です。
あれもこれもと手を広げるより、
「ここ!」と絞って練習することで、子どもの自信にもつながります。
本番までの間、子どもはまだまだ伸びていきます。
焦らず、心の安定を大切にしながら、親子で一歩ずつ取り組んでいきたいですね。
まずは資料で雰囲気をチェック
<資料請求でもらえるもの>
・最新アプリ教材〈3つ〉がすぐに無料で遊べる
・紙のワークブックも自宅に届く(無料)
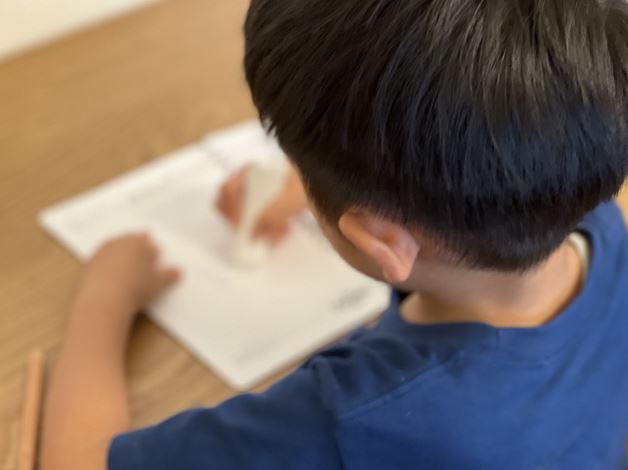




コメント