「お話の記憶」ってどんな問題?どうやって練習すればいいの?
初めて取り組むと、親も子も戸惑うことが多いですよね。
この記事では、我が家が実際に取り組んで効果を感じた「お話の記憶」の練習法や、苦手克服のヒントをたっぷりご紹介します。
どんな問題が出る?

試験の形式
「お話の記憶」のペーパーは、先生や録音された音声で短いお話を聞くところから始まります。
そのあと、聞いたお話の内容について先生から質問があり、ペーパーに〇をつけたり、しるしをつけたりして答える形式です。
つまり、お話をしっかり聞いて覚え、その内容をもとに答える問題なんです。
どんなことを質問されるの?
「お話の記憶」では、聞いたお話の内容について、このような質問が出ることが多いです。
- 数に関する質問
例:「バスに乗ったのは何人ですか?その数だけ〇を書きましょう。」 - 順番に関する質問
例:「2番目にゴールしたのは誰ですか?合う絵に〇をつけましょう。」 - 出来事の内容に関する質問
例:「うさぎさんは何を食べましたか?合う絵に〇をつけましょう。」 - 季節に関する質問
例:「このお話の季節はいつですか?同じ季節の絵に〇をつけましょう。」
このように、登場人物や順番、細かい出来事、季節など、具体的な内容をしっかり覚えておかなければいけません。
見られている力
「お話の記憶」では、次のような力が必要です。
- 記憶力:聞いた内容を正確に覚える力
- 集中力:お話を最後までしっかり聞き続ける力
- 順序立てて考える力:出来事の流れを整理して理解する力
- イメージ力:お話の情景を頭の中で思い浮かべる力
- 語彙力・季節の理解:季節のキーワードや言葉の意味に気づく力
「お話の記憶」は総合的な力が試されます。
この単元が得意になると、他のペーパーにもきっと良い影響が期待できますね!
苦手の原因と我が家の対策
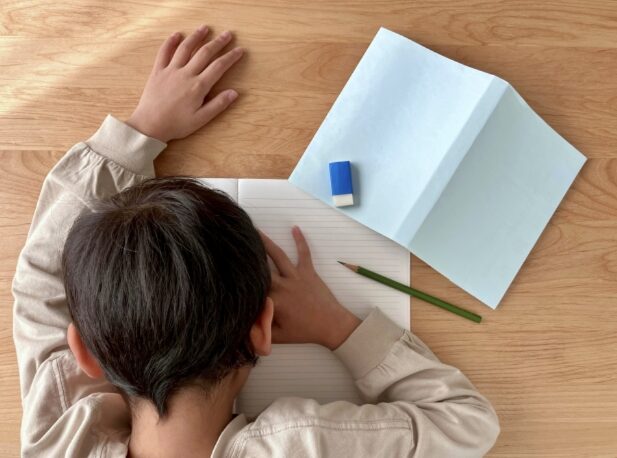
「お話の記憶」が苦手になってしまう原因を、我が子の体験から探ってみました。
集中できていない(ちゃんと聞いていない)
最初のころの我が子は、なんとなく聞いているだけで、質問をしても「え?なに?」という反応…。聞いているようで、実は流し聞きしている状態でした。
つまりお話に全然集中できていない(聞いていない)状態です。
そこで、問題を読み上げるときに重要なキーワードをあえてゆっくり話すように工夫。「ここが大事なんだよ」と自然に意識させるようにしました。
さらに、同じ問題を繰り返す練習も効果的でした。
慣れてくると子どもが「これ簡単かも!」と前向きに思えるようになり、苦手意識をやわらげるきっかけになりました。
言葉の意味が分かっていない
例えば、「門松づくりをしました」と聞いても、そもそも門松が何なのか分からないと、お話の内容も季節感もイメージできませんよね。
同じように、「お月見をしました」と聞いても、それが秋の行事だと知らなければ理解できないこともあります。
我が家では、お話の記憶の問題を読み上げるときに、
「この言葉、うちの子にまだ教えていなかったな…」
「この行事、ちゃんと体験させていないな」
と気づいたら、すぐにフォローするようにしました。
具体的には、映像や絵本を見せてイメージしやすくしたり、その季節がきたら行事をしっかり楽しむように心がけました。
こうした積み重ねが、自然と語彙や知識を広げることにつながり、「お話の記憶」にも良い影響を与えてくれました。
読み聞かせで楽しく練習♪

小学校受験の「お話の記憶」のカギは、やっぱり日々の読み聞かせ。
大切なのは、勉強っぽくするのではなく、子どもが「もっと読んで!」と言いたくなるような環境を作ることです。
我が家では、図書館をフル活用してたくさんの絵本に囲まれる空間を整えたり、寝る前には子どもが自分で選んだ本を読んだりしてきました。
さらにパパやおじいちゃん、おばあちゃんにも読んでもらうこことを意識!
いろいろな読み方に触れることで、自然と耳を鍛えるようにしました。
本好きになることが、「お話の記憶」対策の第一歩。
まずは絵本の世界を親子で楽しむことから始めてみませんか?
まとめ

「お話の記憶」は、できないと感じたときこそ伸びるチャンス!
苦手を「得意!」に変えるために、まずは毎日1枚の「お話の記憶」のペーパーに取り組む習慣と、本の世界を楽しむ習慣を少しずつ取り入れてみませんか?
小さな積み重ねが、自信につながり、自然と力がついていきますよ。






コメント